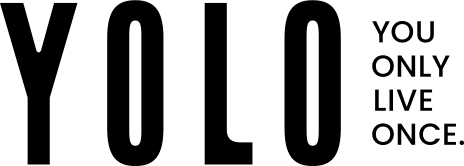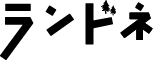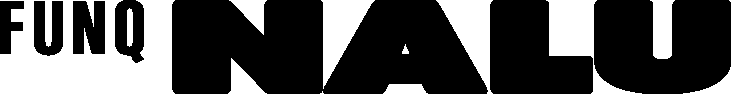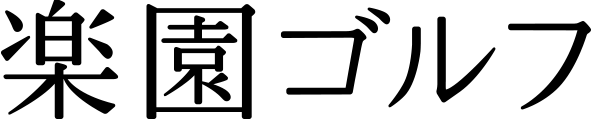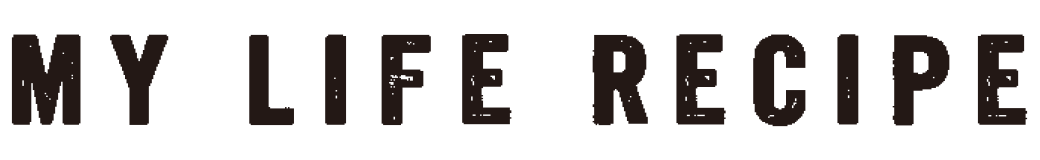うそでしょ…スマホ依存だと「デジタル認知症」に
YOLO 編集部
- 2024年02月19日
Index
デジタル認知症の仕組みとは?
社会的に「スマートフォン依存」が加速する中、「デジタル認知症」という現象も起こっています。デジタル機器に没入しすぎてしまうと、計算や漢字の書き取りなど、以前は自分の頭でしっかりと考えていたことが不必要になります。そのことによりものごとを忘れやすくなったり、思考力や記憶力が低下したりするのです。
また、SNSやメールは、人間の脳内の「報酬系」と言われるエンドルフィンやドーパミンを活性化させる作用があると言われています。それらが過剰分泌されることにより脳内物質のバランスが崩れ、神経細胞が死滅し、その疲れやゴミが蓄積していくのです。

対策のキーワードは「アナログ化」と「ブレインフード」
デジタル疲れを起こしてしまった脳を回復させるために、できることは何でしょうか?
1:休息
デジタルデトックスです。休日はスマートフォンやパソコンを使わないようにする、というのが最も効果的。最初は「電車内でスマートフォンを使わない」「簡単な計算は手元で行う」など、簡単なルールを自分で定めるのがオススメ。
2:食事
ブレインフードの摂取。ブレインフードとは、脳の活性化のために必要な栄養素や、脳機能障害を予防するための食品のこと。これらの食品を積極的に 摂取することによって、脳のケアを行うことができます。
例えば、DHA(ドコサヘキサエン酸)という成分が多く含まれる鯖や秋刀魚といった⻘魚。DHAは、脳の神経細胞を活性化させたり、 傷ついた神経細胞を修復したりする効果があります。
ポリフェノールが含まれているチョコレートや赤ワイン、PS(ホスファチジルセリン)という成分が含まれている大豆もオススメ。
3:睡眠
脳のケアには、睡眠の質を上げることがとても重要となります。それは、睡眠中の脳の活動の一つに老廃物の排出があるからです。成人は睡眠時間を最低でも6〜7.5時間取ることが必要です。
また、きちんと歯を磨くこともとても重要。⻭周病菌に含まれる毒素は、記憶をつかさどる海馬に「脳のゴミ」を増やし、 認知症の症状を悪化させると言われています。歯磨きが脳のケアになるなんて、意外ですね !
※1 博報堂DYメディアパートナーズメディア環境研究所「メディア定点調査」による
- Brand :
- YOLO
- Credit :
-
ライター:幸雅子
監修:矢澤一良/早稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構規範科学総合研究所ヘルスフード科学部門 研究院教授。「日本を健康にする!」研究会会⻑として、健康的な食生活のための間食の重要性を説く「機能性おやつプロジェクト」を推進。1972年京都大学工学部工業化学科卒業。2014年4月より現職。ヘルス フード科学、脂質栄養学、海洋微生物学、食品薬理学を専門とする。
Share